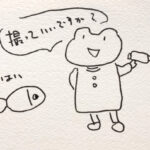出版社を辞めて闘病後、病み上がりだった頃の私は、趣味であったジャズや吹奏楽のコラム、CDのライナーノーツなどの仕事をいただいて、ポチポチと書いて暮らしていた。
その一つに、ジャズ愛好者のためのウェブサイト「KOBEjazz.jp」の原稿があり、スポンサーが富士通テン(現・デンソーテン)という会社だった。テンは、カーオーディオと、「イクリプス」という目玉のかたちをしたスピーカーで人気のメーカーだった。
本社は神戸にあり、お仕事をいただいて間もない頃、関西方面を訪れた機会に、挨拶に行った。
担当者の方に会えればいいなと、軽い気持で出かけたが、このときもまた存外に偉い人が出てきて迎えてくださり、オーディオ工場の中にまで、案内されることになった。
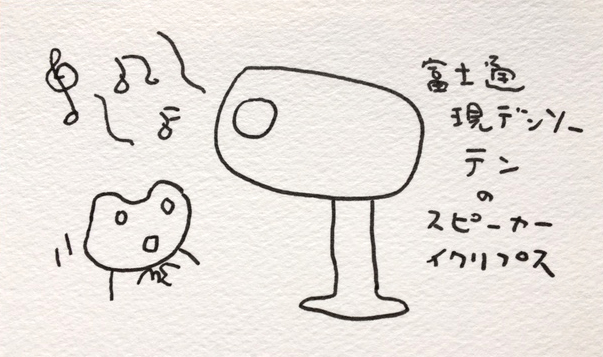
微細な汚れを持ち込まないように専用カッパに着替え、白いキャップをかぶって、現場に入った。
工場内で働く一人ひとりの方がたが、じつに細かい作業をしていることにおどろく。小さな部品を相手にして、真空に近い密室で、一日じゅう閉じこもり、集中している。精密機械を作るという仕事がいかに疲れそうかを、肌で感じて帰ってきた。
物がああして作られる現場を見れば、「物を大切にしなければ」と心の底から思うけれど、作るほうだって作らなければ稼げないので、どんどん作る。
みんなが物を壊したり、捨てたりすることで、物は買われる=お金に変わる。
作った人は壊したり捨てたりしてほしくないはずだが、また作る。
つぎつぎ作る。作りつづけなければ、まわらない、よのなかグルグル。
その一方、作りつづけるのではなく壊しつづけることでまわっているのが、この古紙再生事業会社の工場だった。
工場に足を踏み入れたとたん、目の前に出現したのは巨大な滑り台だ。
大人になってから行ったことないが、サマーランドとかにあるような台が、高い天井を突き抜けそうに、聳えたっている。
恐竜のような、太くて長いクビのいちばん先の顏の部分が、私を見下ろしている。
そのアタマのてっぺんから、ドサーっと、とにかくものすごい勢いで、それはもう大量の、本が落下してくる。
滑り第の下部に、ドンガラガッシャンと落ちた本が溜まり、みるみるうちに積み上がって、山となっていく。
その過程で本は潰れていき、さらにその先で、次の機械に吞み込まれていった。
そのさまは、一種の地獄絵だった。
ここでは、「断裁」がなされていた。
断裁というと、引き裂かれる感じがするが、まさに心が引き裂かれるような、胸の痛みをともなう。
また、「断裁」の実態は、「破壊」であり、まさに「潰す」という言葉がぴったりで、私の肝も潰れた。
私はしばらくその場に佇んで、背の高い機械と、砕かれていく本とを交互に見つめていた。
かつて私の作った本たちも、こんなふうにして死んでいったにちがいない。
あれほど闘って、いくつもの眠れない夜を過ごして、生きた心地のしない日々を過ごしたというのに。
結果その努力は報われたように見えた時があったとしても、しまいにはこうして命を絶たれていったのである。
それでは、私が「編集」についやした時間はいったいなんだったのか?
ついやした時間そのものだけが、生きていた。
時間だけが生き残る? グルグルの中で?
かたちのない、見えないものだけが、残っていく。
<つづく>
*当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。