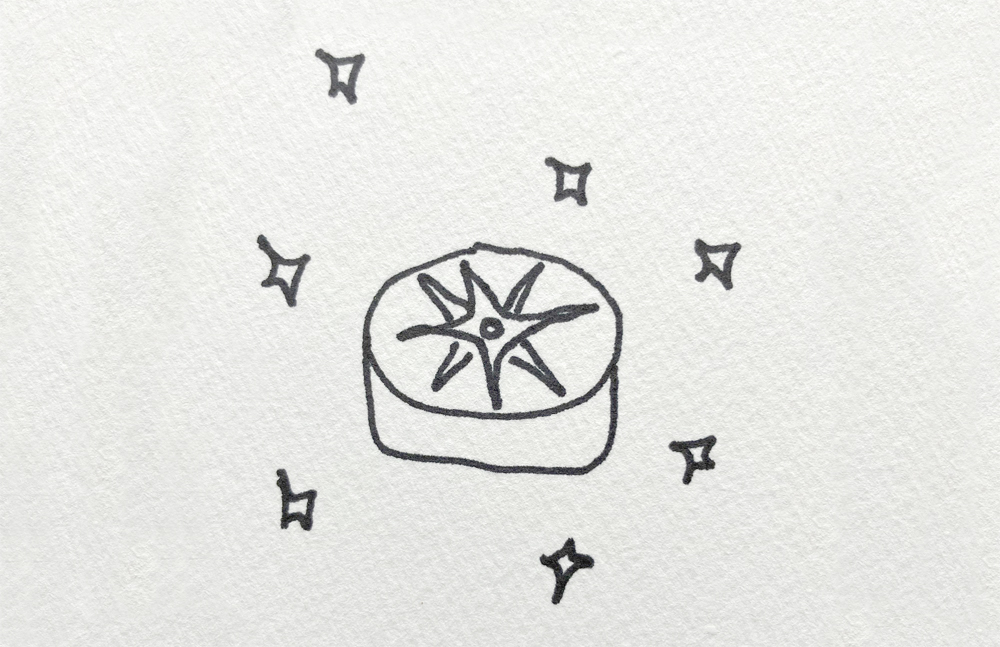ヨーロッパ勢が進出してくるまでは、マラッカを中心とした港湾国家たちが中国、インド、遠くはアフリカ東海岸まで・・・の国々とのあいだに密な交易関係を結んでいた。
これより千年前の時代、すでに中国から西方へつうずるいわゆるシルクロードという陸路が発達していたわけだが、8世紀ごろから造船技術や航海術の向上によって、海上ルートが重宝されるようになっていく。海には危険がいっぱいだが、それを圧してでもラクダより荷のたっぷり積める船のほうがいいやってことだろう。
往来した商品は、金銀銅、織物、香料、陶磁器などなど・・・なかでも陶磁器は、宋代以降、石炭燃料によって強い火力で製作できるようになり、品質がぐんと上がった。

陶磁器は織物に比べて歴史の浅い工芸品だが、姿かたちが残りやすいということで、アジア全域から出土するそのかけらは、多くの研究者を魅了しているようだ。ファーロード、スパイスロードと並ぶ、セラミックロード・・・「陶磁器の道」である。あとでもう少しくわしく、見てみよう。
乗組員100人と一年分の食料をのせた大船の航海には、羅針盤が用いられた。
羅針盤、「大航海」のイメージからヨーロッパ発のような気がしてしまうのだが、最初に用いたのは中国人で、「中国の三大発明」の一つといわれる(ピボット=pivotで磁針を支える形をつくったのはヨーロッパ人)。
中国の「三大」発明は、紙・火薬・羅針盤(紙+印刷技術で「四大発明」とも)。
羅針盤は磁石を使って方角をはかるものだが、はじめは風水に使われていたらしい。それをのちに大活用したのが、明に生きた宦官の航海士・鄭和である。
ところで羅針盤にはちょっとした思い出がある。
あれは2000年ごろだったろうか・・・出版社の編集者をやっていた時代に、羅針盤をさがし回った経験がある。とある作家が、「羅針盤の絵を、本の表紙に使いたい」と言い出したからだ。
はじめは、ピンとこなかった。
羅針盤??・・・現在の暮らしには馴染みのないものである。
画家に羅針盤を描いてもらうには、モデルとなる素材が必要だ。
思いを巡らせた末、十代の終わりにデートで行った「夢の島」を思い出した。当時は「ゆりかもめ」もまだ開通しておらず、彼のクルマで連れて行ってもらった。
「夢の島」と呼ばれる付近に「船の科学館」があり、そこに大きな船が展示されていた気がする。あそこに行けば羅針盤もあるはず・・・
そして天気の良い日に会社を抜け出し、夢の島を目指した。
観光客の家族連れや学校見学のチビッ子たちにまみれながら船の中を歩きまわり、操縦席コーナーに張り付いていた羅針盤を見つけると、写真を撮りまくった。半そでの季節だったと思うが、汗をかきかき、作家ご指名の画家が絵を描きやすいように、あらゆる角度から撮影した。
私は大量の羅針盤の写真を用意したが、けっきょく作家の変心で、本の表紙に羅針盤の絵は使われなかった。私の夢の島ロケはいったいなんだったのか・・・と思わないでもなかったが、当時はこんなことばかりの毎日だったので、慣れていた。あの頃の私はどれだけ、ムダ足を運んだことだろう。ムダ足をムダに終わらせないよう、今後の人生で回収したい。

ところで「夢の島」、夢の島公式サイトhttps://www.yumenoshima.jp/park/historyによれば、戦時中に土砂で埋め立てられている。戦後、海水浴場がつくられるなどして、いっときは「東京のハワイ」と呼ばれる観光地としての役割も期待されたが、台風や財政難で閉鎖へ。高度成長期になると、東京都内のゴミがいっせいにこの場所へ集められることに。1965年ごろにはハエやネズミが大発生し、江東区住民の生活をおびやかして大問題となった。
その後、「江東区vs江東区以外の都区」のゴミ戦争をへて、1970年代の終わりに自然公園としての「夢の島」に生まれ変わる。荒地や乾燥につよいユーカリが植えられて緑あふれる「夢の島」になった。ユーカリは、コアラの餌になるなどして重宝された。
平成の前年には「夢の島・熱帯植物園」がオープン、私がデートで行ったのはこのころだと思うのだが、それから時は流れ、極めつけのTOKYOオリンピック2020をへて、当時のパークの様子は失われてしまったらしい。
羅針盤の発明のみならず、季節風の知識もヨーロッパ発ではなく、このころの「陶磁器の道」の航海ですでに利用されていた。大航海時代のイメージから、なんでもかんでもヨーロッパがすごいと思ったらおおまちがいだ。
マラッカ海峡も、大航海のもっとずっと前からホットスポットであった。マラッカを境にして、風向きが変わる。逆になる。その、「風待ち」の場所。こう書いていたらなんだか自分まで「風待ち」しているような気がしてきた。人生の羅針盤はマラッカにある。
<つづく>
参考文献 『鄭和 中国とイスラム世界を結んだ航海者』(著・寺田隆信、清水書院)
*当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。