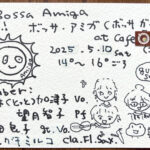かつて「ノブゴロド」という国が、あったという。
いまのロシア北西部あたり。これが、ロシア人のつくった最初の国だといわれている(862年)。
「ノブゴロド」のノブはNEW(ロシア語でノーヴィ)、ゴロドは町(ロシア語でゴーラダ)。つまり「新しい町」だ。
その後、東スラブ人が今のウクライナ・キーウあたりを首都として、「キエフ・ルーシ公国」を建国した(882年)。この「ルーシ」が「ロシア」の語源、しかしこの国はその後の内紛や他民族の侵攻によって、崩壊してしまう。
旧ルーシ領土は遊牧民族らに浸食されていき、モンゴル軍の襲来を受ける。その親玉が、チンギス汗だ。
チンギス汗の死後、その子どもたちがユーラシア中央部をおさめてゆくことになるのだが、彼らが暴れまわり、ロシア南方の草原のトルコ系遊牧民も統合していく話は、前にも書いたかもしれない。彼らはまとめて「タタール人」とよばれた。中国では「韃靼人」と表記される。
「ダッタン人」。
彼らは、旧ルーシの人びと(=ロシア人)をいためつけて支配下におき、重税と労役を課した。これが、第78回「永楽帝の蒙古親征」にも書いたいわゆる「タタールのくびき」で、ロシア人は、その暗黒の時代を「くびき」(頸木=牛馬を扱うときにかれらの首にあてがう木)にたとえた。「タタールのくびき」時代は、250年にもおよんだ。ダッタン人とロシア人の因縁とは、深い。
シベリア年代史によると、「ノブゴロド」の民は、9世紀には北極海に出て、ヤマル半島を横断し、オビ川めざして進んでいった。
11世紀ごろにはウラル山脈を越えてオビ川に達し、ユーゴル地方のユグラ族という人たちとさかんに交易をするようになる。
わがファーロードのテーマ、「毛皮交易」だ。クロテンの往来が、ロシア・シベリア史を運んでゆく。
ノブゴロド人は毛皮を提供し、ユグラ族からは鉄製の斧やナイフを受け取った。そのうちユグラそのものが欲しくなり、ユグラの地を攻めた。
しかし多くのノブゴロド人がユグラに殺られる。それもやっぱり毛皮のためで、諍いの種はつねに毛皮、毛皮、毛皮、毛皮・・・とにかくどれほどの犠牲を払おうと、血を流そうと、とにかく毛皮が大事だったようだ。クロテンにはとんだ迷惑であるが、それほど、このあたりの土地が寒かったということだろう。毛皮なしでは生きられない、毛皮は身を守るすべであると同時に、換金力の高い物品だった。
クロテンたちは人間という生き物がこの地に進出してしまったことを、恨むよりほかない。
毛皮商人たちの商いを支えたのが、「コサック」と「先住民」だが、まず、コサックから行こう。
これも前に書いたかもしれない。繰り返しになるが、古代ロシアからユーラシア南部の大草原で暴れまわっていた騎馬戦闘集団で、古くからのヤクザのような、用心棒のような、血の気の多い人たちだった。
コサックダンスのコサック、といえば、「ああ、あれかぁ・・・」とイメージしてもらえそうだ。日本でもおなじみのロシア民謡「ステパン・ラージン(ステンカ・ラージン)」は、人名である。彼の登場はロマノフ朝に入ってからなので、ちょっと話の先を急ぐことになってしまうが、ステパンは「ドン・コサック」というチームに所属していた。ドン川という、黒海に注ぎ込む大河が、ロシア南部にある。南部なのでタイガ(針葉樹林)でなくステップ(草原)の地域で、草原を馬で駆け、戦うことが仕事であった。ステパン・ラージンはそのチームの首領=ドン(アタマン)だった。

コサックなしで、ロシアの拡大はありえなかった。
ロシアが領土を拡大、つまりシベリアを獲得できたのは、コサックたちが先兵となり、土地の防人となったからだった。
シベリアの用心棒、もとはといえばロシアの農民。自由を求めて、地主から逃げ出した人びととその末裔である。コサック発祥の地は、旧ルーシのスラブ諸公国と黒海の出入り口、クリミア半島あたりといわれている。そこに「ブロドニク」というスキタイ系の民族がいて、コサックの起源だとみなす説がある。彼らは常に周囲の遊牧民の襲撃を受けていたので、どんどん強くなった。
粗末な武器で応戦するうち、脱走兵などプロ兵士や逃亡農民が加わって、さらに力をつけ、なにものにも支配されない自由民集団として、さまざまな民族を仲間に引き入れながら一大勢力に成長していく。資金源は、クロテンだ。
タタールのくびきを突破して、15世紀半ばにノブゴロド地域を統一したのは、モスクワ公国のイワン大帝(三世)。
彼の孫が、イワン雷帝(四世・在位1533~1584)である。
彼は分立していた諸国をモスクワ大公国に併合し、国名を「ロシア」とし、ロシア帝国の基礎を固めた。彼が国家統一をすすめるなかで、コサックたちも国家権力に取り込まれていく。
<つづく>
参考文献
『シベリア』森本良男著 築地書館
『コサックのロシア<戦う民族主義の先兵>』植田樹著 中央公論新社
『シベリアの歴史』加藤九祚 精選復刻紀伊国屋新書
*当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。