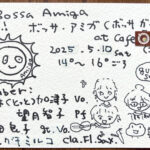2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻は、大きな転機だった。
コロナ禍で変わらざるをえなかったはずの人びとが、あまり変わることができず、コロナ以前をひきずったまま、世界戦争のニュースを聞いた。
冷戦時代よろしく飛行機はシベリア上空を飛ばなくなり、かつての交流や活動ができなくなり、モノの値段は上がり、仕事は減り、メディアに於いても、生活圏でも、<善・悪/敵・味方>の論理で戦争が語られることが多いなか、私の周囲でも、歴史の複雑さをふまえて議論できる人は居場所を失っていった。「ロシアを悪・ウクライナを善」とする人が巷にあふれ、私のような日露親善的活動をめざしていた者も、肩身の狭いおもいをすることがふえた。
私自身、いったい何をやりたかったのか、自信を失くしてしまった。
出版社を退社してひとりになって、無我夢中でやってきたこの十余年はなんだったのか。
仕事も来ないし、活動もできない。もう、ぜーんぶ、やめちゃおうかな・・・だいたい、会社であれば、定年なのだ。私が、「やめます」と言ったところで誰も困らないし、誰も傷つけない。
・・・・かといって、これやめて、なにやるの?
長らく演奏活動は休止してきた。吹いたら書けなくなるんじゃないか、そう思って必死で机にしがみついてきたけれど、それでたいした結果を出せないまま、交流さえ閉ざされる時代に入り、いよいよ自分の勝手な思い込みだけで踏ん張ってきたファーロードは道半ばにて終了するしかないのか・・・
そんなところへ、お声がかかっておどろいた。ロシアのクロテンでお仕事をいただくのは、ほんとうにひさしぶりのことである。
まだたったの十年ほどだが、「ロシアについて」あるていど勉強してきた私にしてみれば、東部四州が彼らにとってどれだけ大事な場所であるかを承知していた。したがって日々ワールドニュースを追いかけながら、ああ、この戦争は、とうぶん終わらないだろうなあ・・・とつくづく思っていたから、クロテンのことも棚上げにしていたのである。
ありがたきご縁からクロテンの件をやることになったが、そもそもクロテンはどのようにして私の心を占めてきたのだったか。
それをおさらいするために、自分の本をひさしぶりに読んだ。
『毛の力 ロシア・ファーロードをゆく』(小学館・2014年)。
とてもいい本だった、と思った。
と同時に、ずいぶん変わった本だと、出版された当時、よくそう言われたものだったが、自分でもそのとおりだと思った。よくこれを出してくれたなあ・・・ありがとう、と、ここであらためて担当編集者氏への感謝をのべておきたい。

イルクーツク・バイカル湖畔
私は2009年の春からガン闘病をしたが、その後、体力が回復すると、昼間は家事をしたり、ジャズ雑誌に原稿を書いたり、レコード会社や出版社に呼ばれて、人物インタビュアーや編集アドバイザーのような仕事をして、日々を過ごしていた。
そうこうするうち、週刊ポストの新里(にっさと)さんから連絡がきた。
新里さんは、私の最初の著書(乳ガンの闘病記『毛のない生活』ミシマ社)が出版された時に知り合った人だったが、連絡をもらったのはひさしぶりだった。
そのころ私が顧問として出入りしていた出版社まで新里さんに来てもらい、近所のイタリアンレストランでランチをした。
真正面から向き合うと、いきなり彼はこう言った。
「ノンフィクションを書きませんか」
いまにして思えば、このとき私は飛び上がって喜ばなければならなかった。
それまでは、誰にも頼まれていないものを、勝手に書いていたのである。そこへ週刊誌を出しているような大手出版社の編集者さんが、声をかけてくださった。なにより、原稿を見てくれる人が、登場した。これが最高の幸せでなくてなんであろう。
ところが、私は「ノンフィクション」という言葉に、ピンとこなかった。
あれ? ノンフィクションってなんだっけ?
ノンフィクションとは、たしか“事実”を書くものだ。自分の最初の本も闘病記なので“事実”を書いたものだが、あれ以上の書くべき“事実”ってなんだ? それまで勝手に書き進めていた文章は、どんなジャンルか不明な代物だった。
「なにを書けばいいのかなあ」
と、いちおう聞いた。
「テーマはなんでもいいんですよ、ミルコさんの視点であれば。たとえば全国のマンホールを巡って書くとか」
と、これまた変わったことを言い出した。
すでに自分勝手に書いているものはあったが、『あれは、ノンフィクションじゃないよな・・・』。
現段階でわけのわからないものを提示して、この話がおじゃんになったら困る。
「考えてみるね」
そうこたえるのが精一杯だった私を、新里さんはまんまる目でふしぎそうに見たあと、山盛りのパスタをものすごい勢いで食べ、私の残した分まで平げて、「あー美味しかった。じゃあまた連絡しますね」と言って額に滲んだ汗をハンカチでていねいにぬぐい、去って行った。
しばらくして、新里さんはまたやってきた。
私の真正面に座り、まんまる目で私を見つめる。
「テーマはどうしましょう?」
「シンガポールに行ってたんだけど、その話はどうかなあ?」
と言ってみた。すると新里さんは、「テーマはなんでもいい」と言っていたわりに関心を示さず、う~ん・・・と考え込んでしまった。
なんど会っても私たちの話はあまり噛み合わず、しかしその間、彼は愚痴を言わず、人の悪口も一切言わず、うわさ話もしない。彼が疲れたと言うのもきいたことがなかった。ものすごく忙しいはずなのにおくびにもださない。
もしかしたら・・・、彼が私に書いてほしいテーマって、私のいた出版社のことなんじゃないかと、ふと思った。
そう気づいた私は一瞬、編集者時代の冴えを取り戻したかと思いきや、ぜんぜんちがった。そんなものより、もっと良いことを彼は思いついた。
「シンガポールじゃなくて、ロシアはどうですか?」
新里さんのこのひとことが、私の世界をぐんと広げることになる。
<つづく>